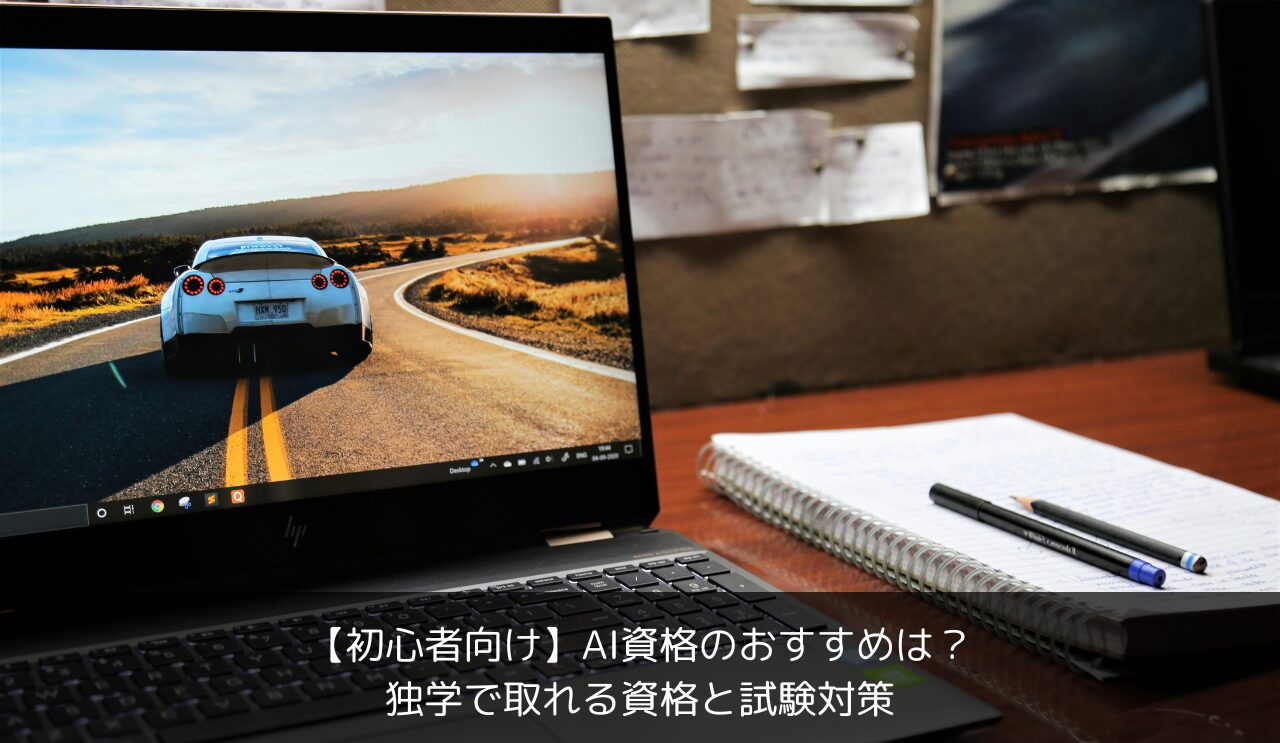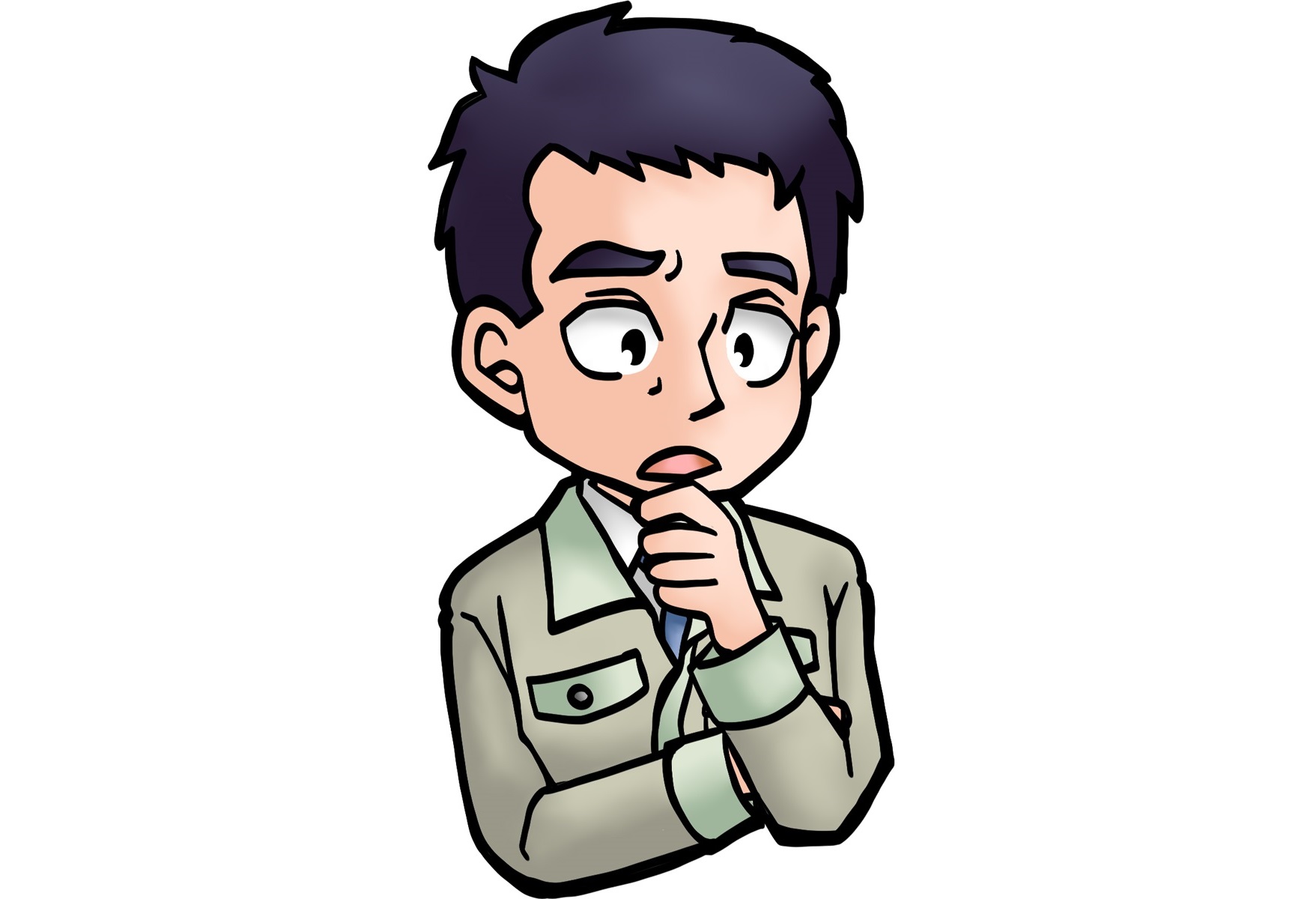
- AIに興味があるが、何から始めればよいかわからない初心者
- IT業界未経験だが、AI関連のスキルを身につけたい人
- 転職やキャリアアップのためにAI資格を取得したい人
- AIエンジニアを目指している人
こんにちは、もと(@moto_log88)です。
AI技術の発展に伴い、AI関連の資格が注目を集めています。しかし、「どの資格を取ればよいかわからない」「初心者でも独学で合格できるの?」と悩む方も多いでしょう。
本記事では、初心者向けのAI資格を厳選し、それぞれの特徴や試験内容、難易度、勉強法について詳しく解説します。独学で合格を目指せる資格も紹介するので、AIスキルを身につけたい方はぜひ参考にしてください。
AI資格を取るメリットとは?
AI資格を取得することで、AIやデータサイエンスの知識を体系的に学ぶことができ、キャリアアップや転職に役立ちます。特に未経験者や文系の人でも挑戦しやすい資格が増えており、基礎知識を身につけるための第一歩として有効です。また、資格取得は履歴書や職務経歴書に記載できるため、IT業界への転職やスキル証明にもなります。
初心者向け!独学で取れるAI資格おすすめ4選
ここでは、初心者でも独学で取得しやすいAI関連資格を紹介します。
G検定(ジェネラリスト検定)
難易度:★★☆☆☆(比較的やさしい)
G検定はAIの基礎知識や倫理、法律、活用事例などを問う試験で、文系や未経験者でも挑戦しやすい資格です。試験は年に6回オンラインで実施されており、比較的受験しやすい環境が整っています。
試験対策としては、公式テキストや問題集を活用し、過去問を繰り返し解くことが重要です。特に頻出するテーマを重点的に学習し、試験前には模擬試験を活用することで合格率を高めることができます。
Python 3 エンジニア認定基礎試験
難易度:★★★☆☆(やや難しい)
Python 3 エンジニア認定基礎試験は、Pythonの基本文法やデータ型、ライブラリに関する知識を問う試験で、AI開発に欠かせないプログラミングスキルを証明できます。試験は随時実施されており、テストセンターで受験可能です。
試験対策としては、Pythonの公式チュートリアルを活用し、基礎から応用まで幅広く学習することが重要です。また、模擬試験を積極的に活用し、試験形式に慣れておくとスムーズに合格を目指せます。
E資格(エンジニア資格)
難易度:★★★★☆(やや難しい)
E資格は機械学習やディープラーニング、数学基礎などの専門的な内容を問う試験で、AIエンジニアを目指す人向けの資格です。試験は年2回(2月・8月)実施されており、受験するにはJDLA認定プログラムの修了が必須となっています。
試験対策としては、JDLA認定講座で基礎をしっかり固めた上で、参考書やオンライン教材を活用しながら実践的な学習を行うことが重要です。特にディープラーニングの実装経験を積むことで、試験の理解度を深めることができます。
Generative AI Test
難易度:★★★☆☆(普通)
Generative AI Testは、生成AIの基本概念や活用事例、実践的な応用について問う試験で、最新のAI技術を学ぶのに最適な資格です。試験はオンラインで随時実施されており、公式サイトで最新の情報が更新されています。
試験対策としては、公式ガイドブックを活用し、生成AIの基本概念をしっかり学ぶことが重要です。また、実際に生成AIツールを試してみることで、試験の内容をより深く理解できるようになります。
AI資格の難易度と合格率を比較
AI資格の難易度は資格ごとに異なります。以下は主な資格の比較表です。
| 資格名 | 難易度 | 合格率 | 受験費用 |
|---|---|---|---|
G検定 | 易しい | 約70% | 13,200円 |
| Python 3 エンジニア 認定基礎試験 | やや難しい | 約60% | 11,000円 |
| E資格 | やや難しい | 約50% | 33,000円 |
| Generative AI Test | 普通 | 約60%~70% | 2,200円 |
※受験費用、スケジュールは変動する可能性があるため、必ず公式サイトをご確認ください。
独学でAI資格に合格するための勉強法
資格試験に独学で合格するためには、適切な教材と学習計画が重要です。
G検定の勉強法
■公式テキストと問題集の活用
公式テキスト『ディープラーニングG検定 公式テキスト』を精読し、基本概念を確実に押さえましょう。また、問題集を活用して、出題傾向を把握しながら理解を深めます。
■オンライン講座の受講
UdemyやYouTubeなどで提供されているG検定対策講座を活用すると、短期間で効率的に学習できます。初心者向けのコースも多いため、基礎から学ぶのに適しています。

■模擬試験で試験形式に慣れる
本番形式の模擬試験を受けることで、時間配分や出題傾向に慣れることが重要です。おすすめの模擬試験教材には『G検定 最強の合格問題集』などがあります。
Python 3 エンジニア認定基礎試験の勉強法
認定テキストであるオイラリー・ジャパン『Pythonチュートリアル第4版』を活用し、基礎からしっかり学ぶことが重要です。プログラミング演習を積極的に行い、模擬試験を活用することで試験対策を万全にできます。
■公式チュートリアルで基礎を学ぶ
認定テキストである『Pythonチュートリアル 第4版』を活用し、基礎をしっかり学びます。
■模擬試験で試験対策を万全にする
試験対策として模擬試験を活用し、時間配分や問題形式に慣れましょう。
<PyQ>
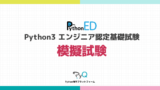
<PRIME STUDY>

<ディープロ EXAM>
E資格の勉強法
JDLA認定講座の受講が必須となるため、まずは講座を受けて基礎を固めることが重要です。さらに、参考書やオンライン教材を活用しながら実践的な学習を行い、試験の理解度を深めましょう。
■JDLA認定講座を受講する
まずはJDLA認定のE資格対応講座を受講し、基礎知識を体系的に学びます。
E資格認定プログラム事業者一覧

■参考書やオンライン教材を活用
試験範囲に対応した参考書を活用し、理論と実装を並行して学習します。
<徹底攻略ディープラーニングE資格エンジニア問題集 第2版>
<ゼロから作るDeep Learning ―Pythonで学ぶディープラーニングの理論と実装>
<スキルアップ模試 AI>

Generative AI Testの勉強法
公式資料を活用しながら、実際に生成AIツールを試してみることで、試験の内容をより深く理解できます。オンラインコースも活用すると、効果的な学習が可能です。
■書籍を購入して独学
受験者が実際に使用した参考書は、以下のサイトに掲載されていますので、参考にしてください。

■実際に生成AIツールを試す
ChatGPT、Stable Diffusion、DALL·Eなどの生成AIツールを実際に使用し、その仕組みを理解します。
ChatGPTユーザーである場合、GPTsを活用した学習も効果的です。
■オンラインコースを活用
おすすめは、AI研究所が運営するAIエンジニア育成講座です。

まとめ:AI資格を活かしてスキルアップしよう
初心者でも独学で取得しやすいAI資格は複数あり、自分の目的に合った資格を選ぶことが重要です。適切な学習方法を選び、効率的に勉強して資格取得を目指しましょう!